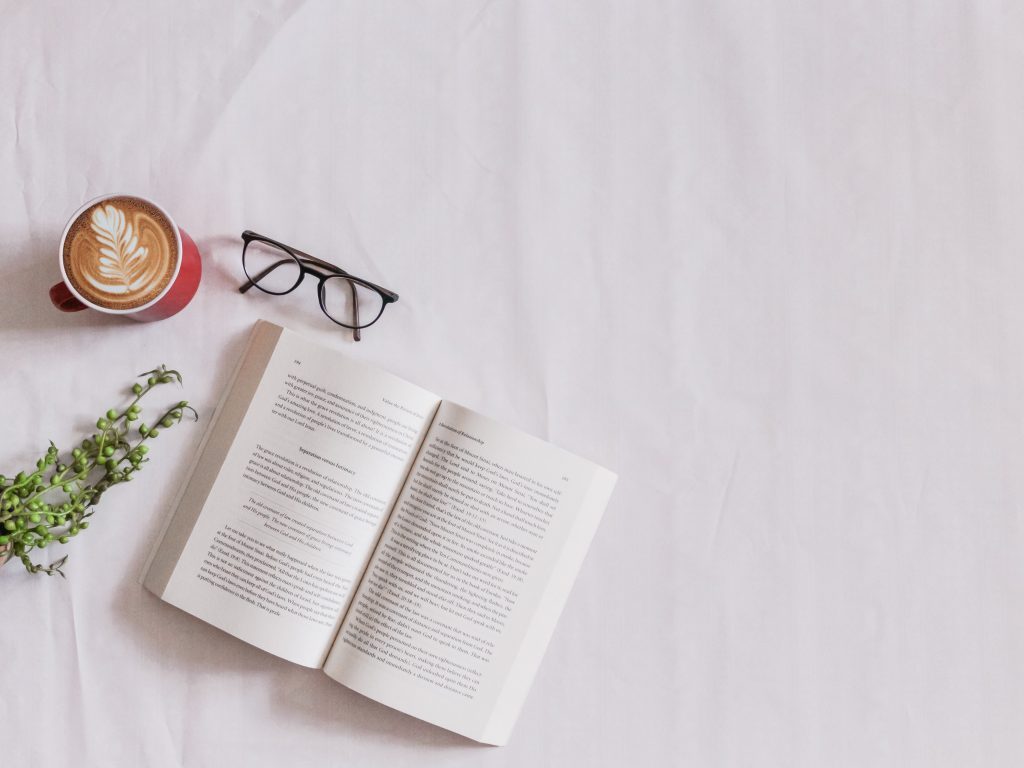こんにちは!
コロナで旅行にいけなくなった分、ちょっとお金のことを今一度勉強した
方がいいのかな、と思い始めた今日この頃なんです。
お金のこと、将来のことを考えはじめたら読む3冊
いくつになっても勉強するのは、遅くない!と信じて、
本屋を散策していて、読んでみたら、なかなか良かったので、紹介します。
漫画 バビロン大富豪の教え
~「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則~
原作は、ジョージ・S・クレイソンの「バビロンの大金持ち」で、
古代の都バビロンで金融のしくみが生まれ、その基本原理は今も変わらずに利用されている。お金と上手につきあうための普遍的な原則とルールを物語形式で語り、90年以上たった今も世界中で翻訳されて、いまなお読者を増やしつづけている。
さらに、この原作を漫画にしているので、すごい読みやすくって、大切なことを教えてくれる
名著だなと感じました。
お金や金融の仕組みができる中で、「お金を上手につきあい」ながら、
「人生の幸せとは?」「なぜ、働くのか」っていう人生についても考えさせられる内容になっています。
となりの億万長者
億万長者とは、実際どんな人々なのか?―アメリカ富裕層研究の第一人者であるスタンリー博士とダンコ博士は、1万人以上の億万長者にインタビューとアンケートをして、資産や年収、職業、消費行動のタイプを徹底的に調査。結果は驚くべきことに、彼らのほとんどはありふれた職業と家庭をもつ「普通の人々」だったのだ!では億万長者でない普通の人々や、所得は多くても資産の少ない人々と、彼らはいったいどこが違うのか?本書は、そうした本物の億万長者の日常の暮らしぶりから学ぶべき「7つの法則」を導き出し、成功と幸福を手に入れたい読者に伝授する。多くの読者を得た実績あるロングセラーが、コンパクトな“新版”として登場!
大富豪とか億万長者って、遠い存在や、事業で成功した人、もともと資産家の家庭に生まれ、それを受け継いだ人を想像するんですが、「となりの」億万長者っていうタイトルにまず興味がわきます。
「そんなに身近にいるのかな?」って思ったんですが、よく考えたら、億の資産を持っているだろうなという人は、頭に浮かぶんですが、そういう人たちって、結構、普段は質素だったりするんですよね。貧乏くさいとかケチっていうのではないんですが、私がそれぐらいの環境で生活しているなら、きっともっとお金にルーズになっちゃうだろうなと思うんです。
ともかく、「倹約!」につとめて、
金持ち父さん貧乏父さん
この本を読んで、「節税」「不労所得」「収入の複線化」など、意識が変わりました。
具体的な方法論というより、ひとまず、今の収入⇒支出というお金の回り方の生活を
この先もずっと続けていていいのかな、とか、
20代からあくせく働いてきて、40代になっていっぱい働いて報酬を増やすっていう
方法は体力的にも限界があるけど、どうしようか。って考えた時に、意識を変えるのに
よい一冊です。
本で学ぶ億万長者の生き方
造園家であり株式投資家でもあった本多静六という方は、
「四分の一天引き貯金法」で資金を貯め、まとまったお金になると投資して
かなりの資産をつくり、しかも、晩年、それは、ほとんど寄付されたというので、
すごい方です。
「四分の一天引き貯金法」は、給料の1/4をはじめに天引きして貯めなさいというシンプルな
教えですが、なかなかできないことですよね。特に、給料の少ない若いころは・・・。
「バビロン大富豪の教え」でも、給料の15%は貯金しなさい。と書いてあります。
また、となりの億万長者では、蓄財優等生と蓄財劣等生にわけて、ライフスタイルやお金の使い方について紹介しているのですが、貯蓄優等生の人のほうが、親からの財産分与などはあてにせずに、
倹約と労働にはげみ、資産を築いたとのこと。(ある意味、夢がある!笑)
「バビロン大富豪の教え」だと、その貯めたお金を活用することや、運用することについても
書かれています。
最後は、じゃぁ、「富豪になったらもう働かなくていいの?」って思うんですが、その答えも紹介されています。
また、「金持ち父さん貧乏父さん」はシリーズ化されていて、有名な本なので、ご存じの方もいると思いますが、私は、
はじめの「金持ち父さん貧乏父さん」を読んで興味がわいたら2冊目まで読めばよいかなぁと思います。
この本は、「資産と負債の違い」「労働所得と不労所得(権利収入)の違い」などが
勉強になります。
私は、一時期結構面白いなぁと思って、「金持ち父さん」シリーズをいろいろ読んだりしましたが、
はじめの2冊がためになったけど、なかなかね、4つのクワドラントをかえていくところまでいけないので、知るは易し、行うは難し・・・というところです。